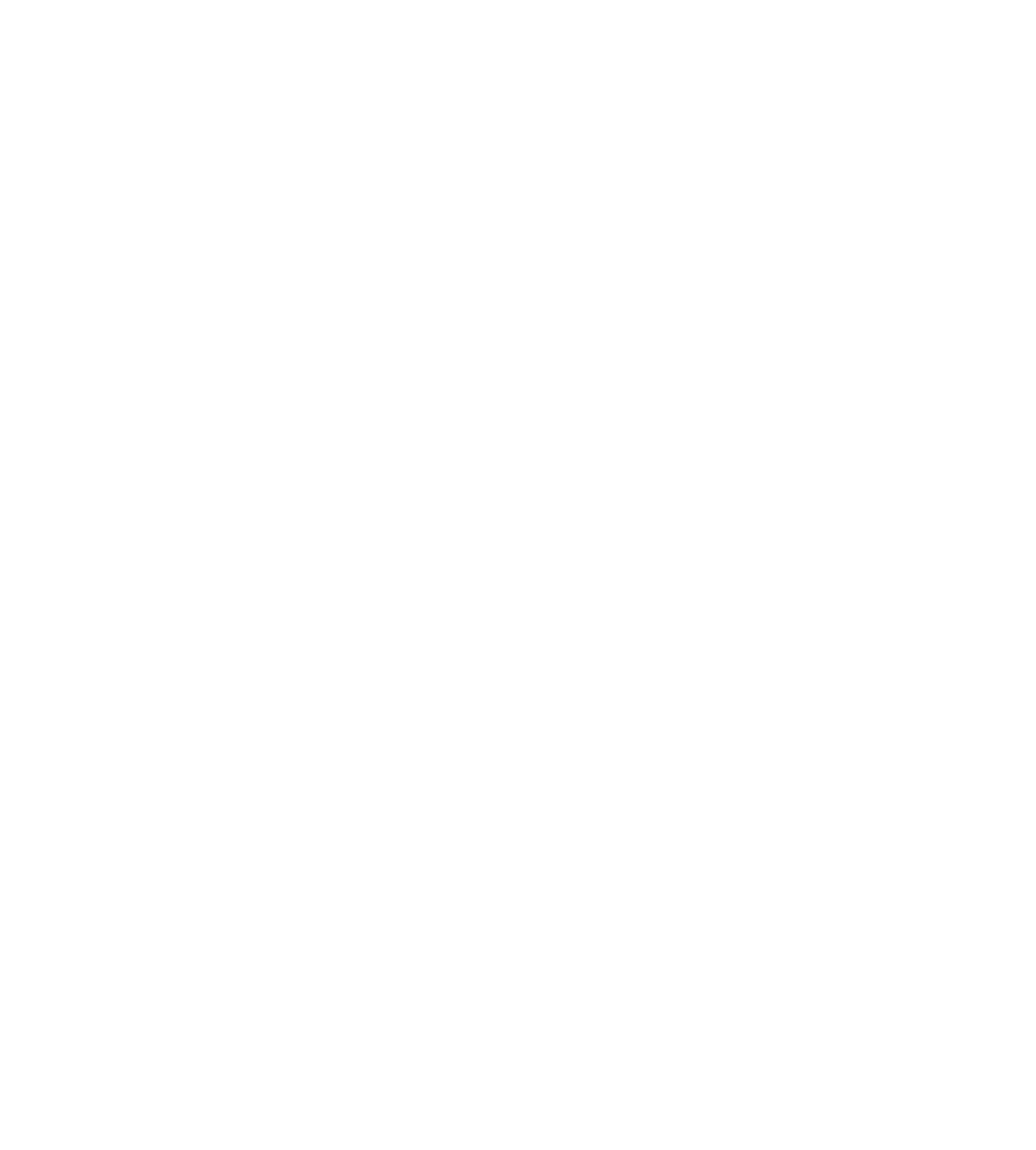こんにちは。葛飾区のE.カレッジ税理士事務所の末松です。
これから独立・開業を目指す方にとって、
最初の大きな壁は「資金調達」ではないでしょうか。
特に日本政策金融公庫などの創業融資を検討している方からは、
☑「そもそも事業計画書ってどう書けばいいの?」
☑「融資を受けるにはどんな準備が必要?」
☑「銀行や公庫に信用してもらうには?」
というようなご相談をよく受けます。
今回は、実際に融資が通った成功例をもとに、
資金調達に強い「事業計画書の作り方」を税理士の視点からわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、あなたの事業もスムーズにスタートを切れるようになります。
この記事でわかること
☑創業融資がどのような制度なのか
☑融資が通るための事業計画書について
☑公庫や銀行の担当者が見ているポイント
☑よくあるNG例とその改善方法
☑資金調達サポートを受けるメリット
(目次)
1)創業融資とは
1-1)新創業融資制度(日本政策金融公庫)
1ー2)制度融資(信用金庫や地方銀行などの金融機関)
1-3)日本政策金融公庫の融資と制度融資が併用可能なケース
2)融資が通る事業計画書に共通する「5つの要素」
2-1)「なぜこのビジネスをやるのか」【事業の目的・動機】
2-2)「どんなサービスを、誰に提供するのか」【ビジネスモデル】
2-3)「どうやって売るのか」【販売戦略・マーケティング】
2-4)「いつ・どのくらい儲かるのか」【売上・利益の見込み】
2-5)「借りたお金をどう使うのか」【資金使途と返済計画】
3、事業計画書のNG例と改善ポイント
3ー1)NG①:売上が急激に伸びすぎている
3ー2)NG②:競合分析が曖昧
3ー3)NG③:資金の使い道がふわっとしている
4、税理士に依頼するメリットとは
5、【決算書の作り方】が融資の成否に大きく関わる理由
5-1)なぜ「決算書の知識」が重要なのか
5ー2)税理士の支援で「数字の説得力」が変わる理由
6、まとめ「融資が通る」事業計画書とは
1)創業融資とは
創業融資とは、これから起業しようとしている方や、起業して間もない方(概ね2年以内)が、開業資金や運転資金を借りることができる公的支援制度の総称です。
主なものは以下になります。
・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」
・地方自治体の制度融資(保証協会付き
金利も低く、担保や保証人なしで借りられる可能性が高いため、
スタートアップには非常に魅力的な制度です。
起業時は、売上がまだ立っていなかったり、信用情報がないため、民間銀行からの借入は非常にハードルが高いのが現実です。
そのため、国や自治体が支援する創業融資制度を活用することが、資金調達の第一歩としては王道の選択肢となります。
1-1)新創業融資制度(日本政策金融公庫)
新創業融資制度は、国が100%出資している日本政策金融公庫が提供する創業者向けの代表的な融資制度です。
新創業融資制度
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 融資元 | 日本政策金融公庫 |
| 融資対象 | 起業前または創業から2年以内の法人・個人 |
| 融資限度額 | 最大3,000万円(運転資金は1,500万円まで) |
| 特徴 | 無担保・無保証人での借入も可能(要件あり) |
| 審査 | 事業計画書、自己資金、経験、人柄、信用情報等を総合的に判断 |
| 金利 | 年1.0〜2.5%程度(変動あり) |
この制度の魅力は、金融機関との取引実績がない創業者でも借りられる可能性があることです。
特に、事業計画書と面談で信頼を得られれば、自己資金が少なめでも通るケースがあります。
1ー2)制度融資(信用金庫や地方銀行などの金融機関)
各都道府県や市区町の地方自治体が行っている制度融資も創業者にとって重要な選択肢です。
こちらは、信用金庫・地方銀行など、地元の金融機関を通じて借入を行い、信用保証協会が保証人代わりになる仕組みです。
制度融資
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 融資元 | 信用金庫や地方銀行などの金融機関 |
| 融資対象 | 創業前または創業から概ね5年以内の法人・個人事業主 |
| 融資限度額 | 創業向け制度融資:1,000万円〜2,000万円程度 中小企業向け融資枠:2,000万円〜5,000万円程度 特別枠(設備投資など):最大7,200万円(東京都など一部) |
| 特徴 | 東京都などでは低金利・優遇条件あり |
| 審査 | 事業計画書、自己資金、経験、人柄、信用情報等を総合的に判断 |
| 金利 | 年1.25~2.85%程度(変動あり) |
制度融資では、自治体が利子や保証料の一部を補助することもありますし、
例えば、東京都では、「創業サポート事業」や「中小企業制度融資」を活用すれば、実質的にあまり利息がかからずに数百万円を借りることが可能になります。
ただし、申し込みの窓口が複数にわかれていたり、書類がやや複雑なため、税理士などの専門家のサポートを受けると申請がスムーズです。
1-3)日本政策金融公庫の融資と制度融資が併用可能なケース
創業融資を検討していると、
「日本政策金融公庫に申し込むか、自治体の制度融資に申し込むか、どちらが良いんだろう?」
という悩みに直面する方が多いです。
実は、日本政策金融公庫の融資と、制度融資は併用が可能なケースがあります。
制度によっては「併用不可」と明記されているケースもありますが、うまく戦略を立てることで、資金調達の幅を大きく広げることができます。
融資制度の併用の具体的なパターン例
パターン①:
【制度融資(地方銀行+保証協会)で設備資金】+【日本政策金融公庫で運転資金】
・店舗の内装費や機械導入など、まとまった初期投資に「制度融資」を利用
・月々の仕入れや人件費など、事業開始後の運転資金には「日本政策金融公庫」を活用
設備資金(初期費用)と運転資金を“分けて調達”することで、それぞれの審査通過率が上がる場合があります。
パターン②:
【制度融資で一部調達】+【公庫で不足分を補完】
・自治体の制度融資で500万円が通ったが、もう200万円必要
・公庫に別途200万円を申請して不足分をカバー
1つの制度に頼りきらず、複数の制度を柔軟に組み合わせることで、融資全体の成功率が向上します。
併用するメリットとしては、調達できる資金額が増え、事業に必要な資金が確保できることです。
また、両方に申し込むことで、どちらかが否決されても、もう一方が通れば最低限の資金確保ができるというリスクヘッジ戦略も取れます。
ただし、併用時の注意点として、同時並行で申し込む場合は、資金使途の重複がないように記載を明確にしましょう。
併用して申請する際には、「併用予定であること」を予め正直に伝えるのが基本です。
自治体の制度によっては、「公庫との併用不可」や「同時申請不可」など制限がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
税理士事務所からのアドバイスですが、制度ごとに審査スピード(公庫は1か月程度、制度融資は2か月以上かかることもあります)や審査基準、利率・返済条件などが異なるため、
「どの制度から申請するのか」というのも重要な戦略になります。
当事務所では、創業者の状況(事業内容・自己資金・希望金額・スケジュール)を丁寧にヒアリングした上で、併用を前提とした資金調達プランの構築・実行支援を行っています。
〝初期費用を制度融資でまかない、運転資金を公庫で補う〟
といった戦略はよく取られています。
重要なのは、【あなたの会社や事業にとって最も通りやすい制度を、目的に応じて選ぶこと】です。
この見極めも、創業支援経験が豊富な専門家のサポートがあると安心です。
2)融資が通る事業計画書に共通する「5つの要素」
ただし、融資が通るかどうかは「事業計画書」の完成度合いに大きく左右されます。
公庫や銀行などの担当者は、あなたの事業が本当に返済能力があるかどうかを、この数枚の紙で判断します。
以下の5つの要素を明確に盛り込むことで、信頼性のある計画書に仕上げることができます。
2-1)「なぜこのビジネスをやるのか」【事業の目的・動機】
創業の背景、業界経験、起業に至った理由は「想い」を伝える最初のチャンスです。
担当者の共感を得られると、審査が有利になります。
あなたの想いや背景を伝えて、信頼を勝ち取りましょう。
銀行や公庫の担当者は、
「この人は、本気でビジネスをやりきれるのか?」を見ています。
記載すべき内容:
☑起業の動機・背景
☑これまでの業界経験・資格・強み
☑なぜ今やるのか
☑どんな想いでやるのか
☑どんなミッションやビジョンがあるのか
記載例:(美容師が美容院を開業する想定)
私は美容師として10年間、大型サロンに勤務し、延べ1万人以上のお客様に施術を行ってまいりました。
その中で、多くのお客様が共通して抱えていた悩みがありました。
それは、
「毎回スタイリストが違って、その都度、同じ質問をされてストレス」
「髪のダメージの悩みを相談したいのに、流れ作業のように施術される」
「SNSで見るような透明感のあるカラーリングができないと断られた」
などの量産型サロンに対する不満や不安でした。
私自身、お客様一人ひとりの髪質やライフスタイル、好みに合わせて施術することを大切にしてきましたが、店舗の都合上、理想の接客や提案ができないこともあり、ずっとジレンマを感じていました。
そこで私は、〝お客様にもっと寄り添った接客ができるサロンを、自分の手でつくりたい〟と強く思うようになりました。
私は、美容師という職業を通じて、お客様の外見だけでなく自信や前向きな気持ちを引き出すことができると信じています。
だからこそ、時間と想いを込めて接客できる空間を、自分の力でつくりたいと考え、今回の創業を決意いたしました。
単に「収入を増やしたいから創業したい」ではなく、
「あなただからこそ創業する意味がある」ということを伝えることが重要です。
2-2)「どんなサービスを、誰に提供するのか」【ビジネスモデル】
ここでは、あなたのビジネスモデルを見せるパートです。
あなたの事業にかける想いがどれだけ熱くても、
ビジネスモデルの構築の作り込みが甘いと、審査が通らなくなる可能性が高まります。
記載すべき内容:
☑商品・サービスの詳細
☑誰が対象か(性別・年齢・地域・職業など)
☑競合との差別化ポイント
記載例:(美容師が美容院を開業する想定)
今回、開業を予定しているのは、“髪の悩みが深い30〜50代女性”を対象にした完全予約制・マンツーマン対応のプライベートサロンです。
髪のカットやカラーリングだけでなく、髪質の改善に特化したトリートメントをシャンプー後に使用したり、肌質改善に特化したフェイシャルエステも提供いたします。
類似店舗と比較して、施術前後の無料カウンセリングを徹底することで、安心感を与えることに注力し差別化を図ります。
また、ヒアリング時に性格診断に関する質問も取り入れ、お客様に合った髪色を提案します。
個人の肌、髪、瞳の色などの見た目の雰囲気で決めるパーソナルカラーとは異なり、
性格や価値観、ライフスタイルや自己表現の傾向などの内面的な要素から、
「本当はこう見られたい」という内面のニーズからお客様に合った髪色を提案するため、お客様に喜ばれます。
上記のサービスを通して、〝髪や肌が明るく綺麗になると、気分も明るく元気になる〟という感動体験を提供したいと考えています。
商品を説明して終わりではなく、競合との違いやなぜ選ばれるのか、その理由まで明確に言語化することが重要です。
2-3)「どうやって売るのか」【販売戦略・マーケティング】
このパートは、「この事業は本当に売上を上げられるのか?」という再現性と実行力の有無が判断されるパートです。
単なる集客手段の列挙ではなく、「戦略性」「実現可能性」「数値目標」「ビジネスの収益設計」まで落とし込んでいるかが、審査通過のカギになります。
記載すべき内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 集客チャネル | SNS、HP、MEO、広告(Google、Meta広告など)、チラシ、紹介、DM |
| 初回導線 | 無料相談、お試しクーポン、初回特典 |
| リピート設計 | 回数券、リピート割、次回予約特典 |
| 顧客管理 | 顧客管理システム(Salesforce、GENIEE SFA/CRMなど) |
| 単価戦略 | 基本メニュー価格、オプション価格、セットメニュー設計 |
| 数値目標 | 月間の新規集客数・予約数・リピート率 |
| LTV戦略 | 単価×リピート回数=LTV、アップセル、クロスセル |
記載例(美容師が美容院を開業する想定)
開業3ヶ月前からInstagram・LINE公式アカウントを開設し、ヘアケア情報やビフォーアフター写真を毎日発信。フォロワー1,000人を目標に、Googleマップ上でのMEO対策(口コミ依頼・写真投稿)も同時に実施。チラシを作成し、ポスティングも行います。
集客チャネルと顧客管理にはホットペッパーを使用し、誕生日には誕生日割のクーポン発行で、再来店率を上げます。
初回来店は「パーソナルカラーカウンセリング+カット+トリートメント」を割引価格で提供(初回単価:16,000円)。LTVを上げるために、来店時には、「半年以内に3回通うとフェイスマスクプレゼント」「誕生日割などの割引クーポン」などリピート設計を導入。
広告費は、初月10万円(ホットペッパー+ポスティング)を想定し、初月予約20件、2ヶ月目30件、以降月平均40件を目標に設定。
客単価は平均20,000円、平均リピート回数が3回、リピート率が60%、LTVは33,600円を想定しています(LTV = 20,000円 ×(1 + 0.6 × 3)- 4000= 52,000円)
また、開業予定地は1km圏内に美容室が約12店舗あり、その多くは20代向け・大型サロンです。
私のサロンは30〜50代女性向けの髪質改善特化型・完全予約制であり、競合とは差別化されていると考えています。
商品やサービスごとの基本価格、フォロワー数や広告費、予約件数などの具体的な数値を記載することで実現可能性を示しましょう。
また、「認知→来店→リピート」の流れを具体的に記載することで、顧客行動がシミュレーションできます。
他の美容室にはない特徴を明記し差別化を言語化し、客単価やLTVの構造を明確にしましょう。
融資審査において、「売上の見込みが現実的かどうか」は収益計画の“生命線になります。
集客やリピート戦略が不明確だと、どれだけ事業への想いが強くても「返済が不安」と判断されてしまいます。
事業計画書では、〝マーケティングの基礎を理解し、実行できる人〟だと伝えることが、融資獲得の近道です。
審査員が納得しやすい計画書には、「市場を把握し、競合との差別化が明確になっている」という要素が欠かせません。
市場や競合調査も積極的に取り入れ、説得力を上げましょう。
2-4)「いつ・どのくらい儲かるのか」【売上・利益の見込み】
このパートでは、単なる希望的観測ではなく、「計画に基づいた現実的な数値」を示しましょう。
銀行や公庫の担当者が知りたいのは、この3点です。
①売上が本当に上がるか?
②利益を残せるのか?
③借入金を返済できるのか?
記載すべき内容
☑月次の売上(客数 × 単価)
☑月次の経費(固定費、変動費)
☑月次の利益(粗利、営業利益、利益率)とキャッシュフロー
☑黒字化のタイミング
☑返済の見通し
記載例(美容師が美容院を開業する想定)
開業初月は、Instagram、LINE、ポスティング、Googleマップ上でのMEO、ホットペッパーを通じて初月予約20件、2ヶ月目35件、3か月目50件、半年後100件を目標に設定。
客単価は平均20,000円、平均リピート回数が3回、リピート率が60%、LTVは33,600円を想定しています。初月は4,000円割引のクーポン発行。
(LTV = 20,000円 ×(1 + 0.6 × 3)- 4000= 52,000円)
初月の売上32万円に対し、家賃16万円、人件費10万円(アルバイト)、広告費10万円、返済金などその他経費12万円で合計支出48万円。12万円の赤字スタートを想定しています。
2ヶ月目には、新規来店13件とリピート数12件を合わせて35件、売上44万8千円、
3ヶ月目は、新規来店29件とリピート数21件を合わせて50名、売上88万4千円で黒字転換します。
4ヶ月目の売上想定は、116万円、
5ヶ月目の売上想定は143万6千円。
半年後には100件(新規来店40件とリピート数60件)、月商184万円を見込んでいます。
借入金300万円に対する月額返済は25,000円を想定しており、黒字化以降は返済可能な利益構造となっています。
また、2年目からは社員やアルバイトなどを増員するため、人件費は上がりますが、その分、売上も上がります。
3年分の損益シミュレーション
| 年度 | 年間売上 | 年間経費 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,712万円 | 920万円 | 792万円 | 約46.2% |
| 2年目 | 2,656万円 | 1,552万円 | 160万円 | 約41.5% |
| 3年目 | 3,408万円 | 2,231万円 | 1,177万円 | 約34.5% |
このような表を入れるだけで、審査官が一目で成長イメージを掴むことができるので、非常に有効です。
黒字化のタイミング、数値の根拠が明確であれば、融資担当者は「返済能力あり」と判断しやすくなります。
また、上記の売上予想の内容に加えて、必要な経費の内訳、広告費や人件費なども細かく入れて、楽観的すぎない数字にする必要があります。
また、やりがちな失敗として、売上が急激に伸びすぎたり、経費がざっくりすぎると、
リアリティが感じられないため、「計画が甘い」「把握してない」と判断され、融資が受けられなくなります。
このパートに関しては一人で書くと、数字が甘くなりがちです。
融資を前提とした銀行や公庫の担当者目線での収支計画を組むことで、返済能力の説得力が一気に上がります。
2-5)「借りたお金をどう使うのか」【資金使途と返済計画】
ここのパートでは、「融資金の使い道が明確か?」「返済能力はあるか?」がチェックされます。
また、自己資金ゼロの状態での借入はマイナス評価に繋がるので、可能であれば、総資金の1〜3割は自己資金を用意しましょう。
記載すべき内容
☑融資金の使途の内訳(項目別に金額を表記)
☑融資の使い道の根拠(見積書、相場データ)
☑自己資金額とその出所(貯蓄、退職金、親族からの贈与など)
☑月次返済額と返済期間(元利均等/元金均等)
☑返済原資となる利益計画(黒字化タイミングと利益額)
☑複数制度を使う場合の使い分け戦略
記載例(美容師が美容院を開業する想定)
借入金500万円のうち、店舗内装費に250万円(見積書添付)、美容機器・セット面・シャンプー台等の備品購入に120万円(見積書添付)、広告費として開業前3か月分で30万円(SNS広告+ポスティング+MEO対策)。残り100万円は開業後3か月分の運転資金(家賃・光熱費・シャンプーやトリートメントなどの仕入れ)に充てます。
自己資金は150万円(全体の30%)で、開業資金総額500万円のうち、不足分350万円を融資で賄います。返済は月額60,000円で、黒字化後の月間利益は最低でも10万円を見込んでおり、返済原資に十分な余裕があります。
制度融資250万円を初期費用に、日本政策金融公庫100万円を運転資金に充て、金利負担と返済計画を分散させます。
見積書や根拠資料を添付して金額の信憑性を上げましょう。
また、自己資金を明記し、返済額と利益の比率の記載や、
複数制度の使い分けの記載で金利・返済リスクを管理できている印象を与えましょう。
まとめ
これら5つの要素は、事業計画書の心臓部です。
単に「夢」や「想い」だけではなく、数字・根拠・戦略を織り交ぜることで、審査する担当者に経営者としての信頼を伝えることができます。
特に、④や⑤は、決算書・損益計算・キャッシュフローに関わるため、税理士などの専門家と一緒に作成することで審査通過率が飛躍的に高まります。
3、事業計画書のNG例と改善ポイント
事業計画書のNG例を改善することで、融資の審査通過率を高めましょう。
3ー1)NG①:売上が急激に伸びすぎている
非現実的で、実現可能性が低いと判断されやすいです。
「初月は10件×単価1万円で売上10万円」などの現実的な数字を見せましょう。
3ー2)NG②:競合分析が曖昧
「ライバルがいない」というのは基本NG。
必ず競合他社、比較対象を出し、あなたの強みを具体的に記載してください。
どのような業種にも競合他社は存在します。
調査した内容の精度が高いほど、融資担当者からの評価は上がります。
3ー3)NG③:資金の使い道がふわっとしている
「広告に使います」「初期費用に使います」だけでは不十分。
「◯万円をGoogle広告に」「◯万円は内装費に」と詳細かつ明確に書きましょう。
4、税理士に依頼するメリットとは
創業者が1人で事業計画書をつくるのは大変です。
特に以下のいずれかに当てはまる場合、税理士のサポートが役立ちます。
「数字の裏付けが弱い」
「どこまで詳細に書いていいか分からない」
「融資の審査に通るか自信がない」
「本業の準備で忙しく事業計画書を作成する時間がとれない」
当事務所では、創業融資に強い事業計画書の作成サポートはもちろん、
資金繰り・経理・税務の長期的な支援まで一貫して行っております。
5、【決算書の作り方】が融資の成否に大きく関わる理由
「創業融資は、まだ決算書がないから関係ない」と思っていませんか?
実はそれ、半分正解で半分間違いです。
確かに創業時にはまだ正式な決算書(損益計算書・貸借対照表)は存在しません。
しかし、事業計画書の中には決算書と同様のフォーマットで収支を組むことが求められます。
たとえば、日本政策金融公庫が求める「創業計画書」には、以下のような記載が必要です。
・売上高
・売上原価
・経費の内訳
・当期利益
・借入金の返済予定
これらはすべて、決算書内の損益計算書の構造そのものです。
5-1)なぜ「決算書の知識」が重要なのか
収支のバランスが悪いと、融資担当者は「この人は経営を分かっていない」と判断します。
固定費と変動費の区別がないと、キャッシュフローの見通しが立たなくなります。
借入金返済の原資、営業利益が少ないと、「返済不能」と判断されます。
「まだ決算を迎えていない」創業者こそ、決算書の基本を理解しておくことが重要なのです。
5ー2)税理士の支援で「数字の説得力」が変わる理由
創業融資の審査において、「どれだけ数字に説得力があるか」は、融資の可否を大きく左右します。
中でも、銀行や公庫の担当者が最も注目するのは、
・収支計画(損益)に現実性があるか
・キャッシュフローが適切に管理されているか
・借入金の返済能力があるかどうか
といった「数値の整合性」です。
客単価や利益率が実態とかけ離れてたり、固定費・変動費の区分が不明確、
キャッシュフロー(現金の流れ)と利益の違いが分かってないような事業計画書ですと、
どれだけ良いサービス内容やどれだけ熱い想いがあっても、「返済できなさそう」と判断されてしまい、不通過のリスクが高まります。
当事務所では、事業計画書の段階から、決算書の構造(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)をベースにした「簡易的な決算モデル」を一緒に作成します。
税理士が支援することで、 数字に“根拠”と“実行性”が加わり、
キャッシュフローの視点で資金繰りを設計できるため、黒字でもキャッシュが足りずに倒産、という事態を防ぐことができます。
また、運転資金を含めた資金調達の計画が立てやすく、融資後の実務に直結する「成長型の計画」が作れます。
具体的な支援内容(E.カレッジ税理士事務所の例)
| 支援内容 | 効果 |
|---|---|
| 損益計画(PL)の設計 | 利益の妥当性・返済原資の提示 |
| 資金繰り(CF)計算 | 月次の現金残高を把握・運転資金の不足を防止 |
| 設備投資・費用の明細チェック | 金額の根拠を明確化し、審査通過率を高める |
| 返済シミュレーション | 借入金返済のキャッシュ確保を見える化 |
| 補足説明資料 | 審査官への印象を上げる、面談対策 |
6、まとめ:「融資が通る」事業計画書
創業時の資金調達は、事業の明暗を分ける大きな要素です。
自己流で作るのも大切ですが、「創業融資に強い税理士」の伴走があることで、成功率は大きく変わります。
もし今、
起業は決めたけど何から始めれば…
融資に落ちたらどうしよう…
信頼できるパートナーが欲しい…
という不安が少しでもあれば、まずは無料相談から始めてみませんか?
また、融資の制度は複数を併用することで資金調達の成功率を高めることができます。
創業期は資金がもっとも必要な時期であるのと同時に、実績がないもしくは少ないがゆえにもっとも調達が難しいタイミングでもあります。
「どの制度が一番通りやすいか」を考えるだけではなく、
☑どの資金をどの制度でまかなうべきか?
☑併用できる制度は何か?
☑申請の順番とタイミングは?
といった視点を戦略的に組み立てることで、より高確率で、より有利な条件で資金調達を実現することが可能です。
制度の選定・書類作成・金融機関との交渉を含めて、創業支援の経験が豊富な税理士に一度ご相談ください。
E.カレッジ税理士事務所では、融資が通るためだけの“表面的な数字合わせ”ではなく、
・数字に説得力を持たせる
・資金繰りが続く経営
・実際に利益が出るビジネスモデル
という観点で、事業計画の数値設計を一緒に行っています。
創業時こそ、「数字に強いパートナー」と一緒に設計することで、融資だけでなく、事業そのものが強くなります。
それではまた次の記事でお会いしましょう。